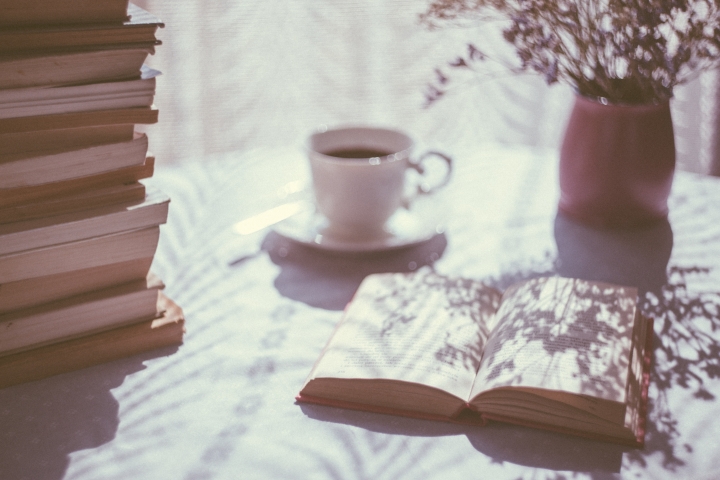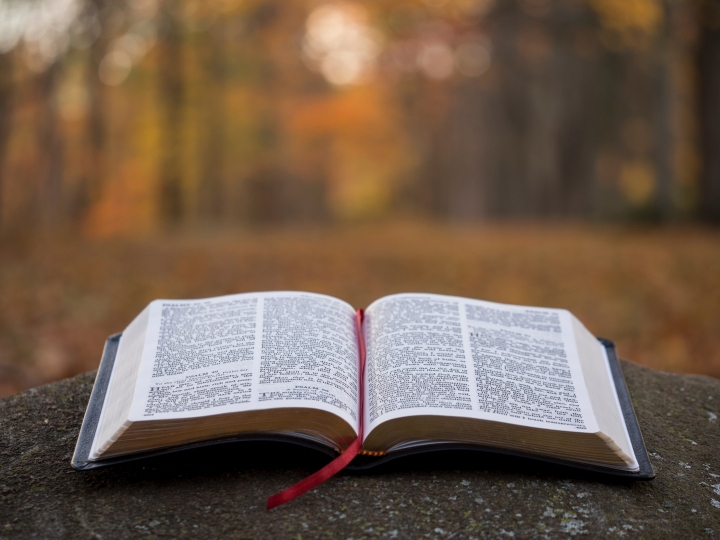「毒親」という言葉に感じる違和感
近年、「毒親(どくおや)」という言葉をよく耳にします。
子どもを束縛したり、コントロールしたりする親を指す言葉ですが、私はこの言葉がどうしても好きになれません。
なぜなら、そこには「親の不器用な愛情」を切り捨ててしまう危うさがあるからです。「毒」という一言で括ってしまうと、そこにある迷いや善意、そして愛情の複雑さが見えなくなってしまう。
私は、長年にわたり受験生やそのお母さま方のカウンセリングをしてきた経験から、
むしろこう言いたいのです。
「毒親なんていない。あるのは、愛し方に迷っている親だけだ」と。
愛情があるから、きつく当たってしまう
受験期は、母親にとっても「心の試験」のようなものです。
子どもの将来を想うあまり、つい厳しい言葉をかけてしまう。
それは支配ではなく、深い愛情の裏返しです。
「今勉強しなきゃ将来困るよ」
「ちゃんと目標を決めて動かないと」
こうした言葉の根底には、「この子に幸せになってほしい」という一途な想いがある。しかし、子どもはその“愛の熱量”をそのまま受け止められず、その結果、親子の間にすれ違いが生まれてしまうのです。
愛情があるから、母親は迷う
母親は、子どもを想うからこそ悩み、迷い、苦しみます。「勉強させるべき?」「信じて待つべき?」どちらの道を選んでも、どこかで罪悪感を覚えてしまう。
けれど、その迷いこそが人間的であり、尊いものだと私は考えます。
完全な親も、完璧な答えも存在しない。
それでも子どもと向き合おうとする姿勢そのものが、すでに愛の証なのです。
哲学が教えてくれる「親子の関係」の本質
哲学者キルケゴールは『死に至る病』でこう述べています。
「人間とは、自己と自己の関係に関係する存在である。」
つまり、人は“関係そのもの”を生きている存在です。
親子の関係も、その一つの形です。
親は「育てる存在」である前に、一人の未完成な人間。
子どもは「育てられる存在」であると同時に、親を映す鏡でもあります。
この「不完全さ」を受け入れたとき、親子の関係は競争や支配を超え、対話と成長の場へと変わっていきます。
フランクルとラカンが示す“愛の構造”
精神科医ヴィクトール・フランクルは、どんな状況にも「人生の意味」を見出せると語りました。
また、フランスの精神分析家ジャック・ラカンは、「欲望とは他者の欲望である」と言いました。
この二人の哲学を通して見えてくるのは、人は他者との関係の中でしか、自分を理解できないということ。
親が子に注ぐ愛情とは、実は「自分がどう生きたいか」をもう一度見つめ直す営みでもあります。つまり、子育ては“自分の人生を哲学的に生き直す”経験なのです。
生まれ持った“よさ”を生かすと、受験はうまくいく
私は長年、受験指導とカウンセリングの両方に携わってきました。
その中で気づいたのは、生まれ持ったよさを素直に生かす子ほど結果が出るということです。
たとえば、誰かを支えるのが得意な子が医療を志すとき、その優しさがそのまま努力のエネルギーになる。
逆に、「偏差値が高いから」「安定しているから」といった外側の基準で選ぶと、どこかで力が続かなくなる。
キルケゴールの言葉で言えば、
「自己と自己の関係が正しくあるとき、人は絶望しない。」
大学受験も、同じです。“なりたい誰か”ではなく、“本来の自分”として挑むとき、
人は最も高いパフォーマンスを発揮できるのです。
「毒親なんていない」という哲学的な視点
私は、母親を責める社会の風潮に疑問を持っています。「過干渉」「心配性」「支配的」──それらはすべて、愛情の形のひとつです。
大切なのは、愛を否定することではなく、その愛をどう表現すればお互いに幸せになれるかを見つけること。
毒親という言葉は、親を“悪者”にしてしまう。
でも、哲学的に見れば、人は誰しも矛盾を抱えながら愛している。
その不完全さを赦す視点こそが、本当の意味での「親の成熟」だと思うのです。
結論──愛があるから、迷っていい
受験期の母親は、子どもを想うがゆえに苦しくなる。
でも、それでいいのです。
愛があるからこそ迷い、愛があるからこそ涙する。
その「迷い」こそ、人間らしさの証。
哲学は、そんな人間の不完全さを肯定します。
そして心理学は、その不完全さを生きやすくする知恵を与えてくれます。
私はこの二つの視点を統合して、「心と現実をつなぐカウンセリング」を行っています。
毒親なんていない。
いるのは、愛し方に悩みながら、真剣に子を思う親だけです。