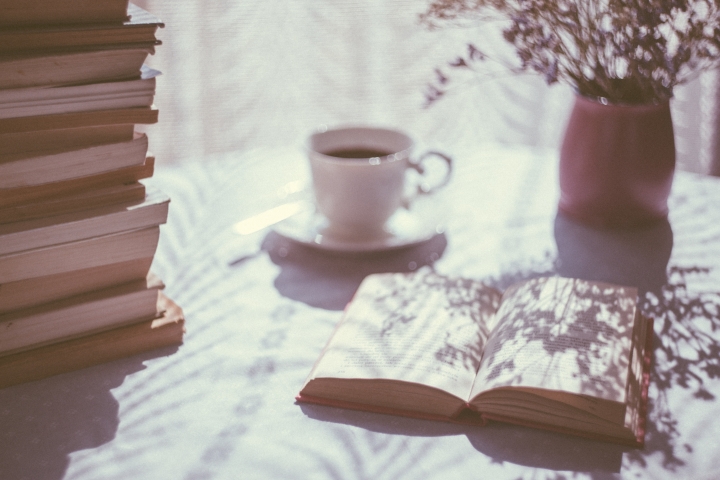「タイパ」「コスパ」という言葉が、当たり前のように使われる時代になりました。
時間対効果、費用対効果を最大化すること。
短時間で成果を出し、無駄を排除し、合理的に生きること。
現代社会では、それが疑いなく「正しい生き方」とされています。
この価値観の背景にあるのは、経済至上主義と科学的合理性です。
数値化できるもの、データで示せるもの、再現可能なものだけが評価され、
制度やシステムとして社会に組み込まれていきます。
逆に言えば、データに上がらないものは「存在しないもの」として扱われがちです。
学校も会社もおなじ
学校も会社も、基本的にはこの論理で設計されています。
成果が測れない活動、目的が曖昧な時間、遠回りに見える思考。
それらは「非効率」「無駄」として、できる限り削ぎ落とされていきます。
しかし、その合理性の中で生き続けたとき、
私たちの心は本当に生きていられるのでしょうか。
実際には、無駄や余白が失われた環境で、
心がすり減り、思考が浅くなり、意欲を失っていく人は少なくありません。
にもかかわらず、多くの教育現場や職場は、この問題を正面から扱いません。
理由は明確です。
「無駄が大事だ」「余白が必要だ」と主張しても、
それを完全に裏づける科学的根拠が存在しないからです。
今の社会では、エビデンスがなければ制度にできない。
データに表れないものは、議論の俎上にすら乗りません。
まさに「それがあった」という事実
けれども一方で、
「ある程度の無駄や余白がなければ、人の心は死んでいく」
そう語り続けてきた人たちがいます。
医学、哲学、自然科学など、分野は違えど、
長い思索と実践を通して同じ結論に至った人たちです。
重要なのは、その主張が科学的に証明されているかどうかではありません。
彼らが実際に、豊かな人生を歩んできたという事実です。
効率一辺倒ではない時間を持ち、
遠回りをし、立ち止まり、説明できないものと向き合いながら、
深く生きてきたという現実です。
もし「無駄がなければうまくいかない」と語る人が現に存在し、
しかもその人たちが人生を通して成熟してきたのだとしたら、
私たちはその無駄を「なかったこと」にしてよいのでしょうか。
そこに科学的根拠があるかないか以前に、
そこに確かに存在しているものを、存在しているまま認める。
私はその姿勢こそが、これからの社会に必要だと考えています。
勉強ができるようになるシステム。
会社がうまく回っていくシステム。
それらを設計する際に、
成果に直結しない時間、目的の定まらない思索、
一見すると無駄にしか見えない余白をあらかじめ組み込んでおく。
効率の外側にあるものを、最初から排除しない。
説明できないものを、説明できないまま残しておく。
それは非合理なのではなく、人間に対して誠実であるということです。
科学が隠してしまったもの
科学的根拠があろうとなかろうと、
まさにそこに「ある」ものを、ないことにはできません。
むしろ、その存在を前提にしてシステムを設計すること。
それこそが、心を殺さずに生きるための一つの方法なのだと思います。
無駄を許すことは、怠けることではありません。
余白を残すことは、後退ではありません。
それは、人が人として生き続けるための、最低限の条件なのです。